| ホームへ | ||||||||||
|
||||||||||
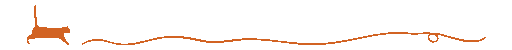 |
||||||||||
|
━━……‥‥・‥‥……━━……‥‥・‥‥……━━……‥‥・‥‥……━━……‥‥・‥‥……━━ |
||||||||||
| 1. | 猫を引き取ってから最初にする事 引き取ったらすぐに、保護主さんやペットショップで【済】と言われていても必ずご自分自身で動物病院で、血液検査、ウィルス検査、検便、虫下し、蚤取り、三種混合ワクチン接種をして下さい。 |
|||||||||
| 2. | 予防接種(ワクチン)と定期検診 子猫は母乳から体に免疫抗体ができますが、生後2ヶ月でその免疫抗体は効果を無くします。 最初の接種は免疫力を高める為、生後2ヶ月後と3ヶ月後の2回受けます(子猫以外でも初めての時は2回接種)。後は年一回接種月を決め、体調のいい日を選んで受けてください。 使用されているワクチンは ①猫ウィルス性鼻気管炎…流感の一種。感染後3,4日で元気がなくなり、くしゃみ・鼻水・よだれを伴う。2,3週間で治ることが多いがひどい場合は衰弱が進み死んでしまいます。 ②猫カリシウィルス感染症…風邪の一種。上記の症状と似ている他に特に唇や舌に潰瘍が出来、3週間以内で回復しますが放っておくと肺炎を起こし子猫では死ぬこともあります。 ③猫伝染性腸炎(猫ジステンパー)…猫汎白血球減少症とも呼ばれる。伝染力が強く子猫など進行しだいでは4,5日で死亡することもあります。食欲がなく、初期は嘔吐と発熱を伴い、白血球が減少して外耳炎などの合併症も起こしやすくなります。脱水症状を起こしますがこの病気は注射による水分補給が最大のポイントなので、素人判断で無理に水を飲ませるのは厳禁、逆に悪化させ危険です。必ず獣医さんへ。 上記の三種で、混合ワクチンになっています。 また、1、2匹までで室内飼育に徹底していれば三種で十分だと思いますが、3匹以上飼う場合は、白血病感染率が高くなりますので、獣医さんと相談して五種にすれば良いと思います【五種混合ワクチン】には【猫白血病ウィルス感染症】の予防ワクチンが入っています。この場合は、最初の接種のみ、1度受けてその半年後にもう1度接種します。 健康診断は最低年一回は受けましょう |
|||||||||
| 3. | 病院の選び方・かかり方 猫の健康を守るには、まず信頼できるホームドクターを作ることが大事です。 そのためには、すでに猫を飼っている人やペットショップに聞いてみることです。 例えば、獣医さんが動物好きなのか・家が近所であるのか・深夜でも緊急事態に対応もらえるのか・猫の状態や投与する薬の詳細などをきちんと説明くれるのか・こちらの質問や不安にきちんと対応してくれるとかも選ぶ時の大切なポイントになります。 その他、簡単な治療するだけで麻酔をかけたり、ろくに症状も聞かないでとにかく連れて来なさいという所や、立派な建物でも診察室の汚れている所なども避けたほうがいいと思います。 また、飼い主側の態度も大切です。何もかも獣医さんにお任せではなく、猫ちゃんの具合が悪い時はよく観察をし、症状を獣医さんに詳しく説明して、お互いの信頼を築いて行くことも必要です。 病院は病気の動物が集まるところなので、病気を貰ってくることもないとは言えません。平気で他人の動物の頭などをなでたりしないで、猫も専用のキャリングバッグに入れて他の動物と接触をさせないようにします |
|||||||||
| 4. | 嘔吐について 猫は消化しにくいものや有害物を飲み込んだり、食べすぎたり急いで食べた時、便秘(便が少ない、硬いなど)の時にもすぐ吐きます。また毛玉を吐くこともありますが、いずれも自然現象で心配いりません。 食事直後に食べた物だけを嘔吐して後は元気でいる場合は消化不良か毛玉(猫は毛玉を吐きたい時に、わざと一気に食べる時があります)ですので大丈夫です。 嘔吐の状態が泡状か液状であったり血が混じっている場合、嘔吐が異常に続く場合は≪嘔吐物を持参して≫早急に病院へ連れて行って下さい。嘔吐物の中に回虫が混ざっていても勝手に判断して虫下しを飲ませないこと。 |
|||||||||
| 5. | 下痢について 下痢には感染性のものと非感染性のものがあり、消化器系疾患の多くは下痢症状が見られます。 非感染性のものには、アレルギー、ストレス、冷え、フードが体質にあわない、等があります。 この場合は、腸を休めるためにも食事を1食抜いて様子を見て、次回の食事はドライフードをふやかしたものを少量にとどめ、調子が戻ればその次の食事から元に戻してやりましょう。 しかし、これでも、改善が見られない時は、たとえ消化不良が原因の場合であっても、たちの悪い慢性の下痢になることがよくあります。下痢はとても治りにくい症状のひとつなので、便をビニールぶくろに入れて持参し、病院に連れて行ってください。 血便が出たり、猫がぐったりしているような場合は感染性の下痢の可能性が高いので、自分で治そうとはせずにすぐに動物病院で診察を受け、その指示に従うようにして下さい。 |
|||||||||
| 6. | 便秘について 異物の飲み込み、腸の機能障害、腰椎欠損症、先天性の巨大結腸症などの疑いもあります。2,3日の便秘なら心配要りませんが、腹部を触ったりすると痛がる場合は、早急に獣医さんに診てもらってください。 |
|||||||||
| 7. | 飲水が多い・多尿である トイレには頻繁に行くが排尿がない場合は結石の疑いが大(オスに多いです)。
嘔吐、下痢の後や軽い日射病状態の時以外で、水を多量に飲んだり、排尿量が異常に多い時は糖尿病や腎臓疾患、 メス猫なら子宮蓄膿症の疑いがあるので早急に病院へ行くことです。 |
|||||||||
| 8. | 食欲不振について 食欲不振が長く続く時は虫歯や歯槽膿漏、あごの筋肉や関節の異常、また内臓疾患も考えられます。 ストレスや環境の変化によることもありますが、その場合は2,3日程度で回復します。 |
|||||||||
| 9. | 目ヤニについて 両目とも目が開かないほど目やにがひどい時は伝染病や感染症の疑いがありますので、明日を待たずに早急に病院へ連れて行って下さい。 ゴミ、ホコリ、ケンカなどで角膜が傷ついた時も涙や目やにが出ます 目ヤニが乾いていたり比較的少量の場合は、1,2日様子を見て治らないようなら病院にいってください。 |
|||||||||
| 10. | 歯石について 飼い猫はほとんど軟らかい物ばかりを食べているので、歯石がたまりがちです。気づいた時に爪でとってやりましょう。 ひどく嫌がったり、歯石が固まってしまっている場合は、定期的に(1年に1回ぐらい)病院で取り除いてもらうようにして下さい。 老猫に多いですが歯周病も歯石が原因です。歯が黄色くなってきたら歯周病になり始めているので気をつけてやって下さい。進行すると、抜歯することになってしまいます。 |
|||||||||
| 11. | 口臭について 臭いがとてもひどい時は歯槽膿漏や口内炎が進んでいて、ひどい場合は飲食出来なくなります。口内炎はウィルス性伝染病や腎炎、慢性胃炎、寄生虫による消化障害などが原因ということもあります。歯石も放っておかないようにしましょう。 |
|||||||||
| 12. | 鼻水について 寝ている時、起きてから30分くらいは鼻が乾いているのは普通ですが、それ以外だと注意モードです。水のような鼻が出てくしゃみをする程度なら軽い鼻炎です。 |
|||||||||
| 13. | 健康管理のチェック ●体温のチェック ●脈・呼吸数のチェック(興奮したり遊んだ後は高いので、静かにしている時に測ること) ●季節ごとのチェック |
|||||||||
| 14. | ストレスについて 猫はデリケートな動物なのでストレスを受け易く、それによって体調を壊し、寿命も短くなりかねません。野良猫等が完全室内飼育の猫と比べて平均5~6年寿命が短くなるのもストレスが原因だと考えられています。 猫は7歳からシニア(老猫)期間に入りますが、それからのストレスは、酷くなると死を招く事もありますので、シニアの猫ちゃんがいる場合は、出来れば環境の変化、特に引越しや新しい動物を同居させる事は避けて下さい。 |
|||||||||
| 15. | 猫が快適に暮らせる温度は 猫は元々砂漠に住んでいた動物で、寒さや多湿に比較的弱い動物です。 しかし砂漠地方は低湿なため、日陰に入れば温度はかなり低くなるので、猫は暑さに強いということではありません。 猫をケージなどに入れておく場合は、冷気が直接猫の体に当たらないように配慮することも必要です。 |
|||||||||
| 16. | 捨猫を拾ったら 衰弱していることが多いので、病院へ連れて行き健康チェックや生後日数のチェックをして貰いましょう。 生後どのくらいかによって食事内容や飼い方を変えてやる必要があります。 成長度の目安 生後10日位までに目が開く。 生後15日位で耳がピンと立つようになり、乳歯が生え始める。 生後21日位でどうにか立てるようになる。 4~5週間位で乳歯が完全に生えそろいます。 生後8週間目頃までは人工哺乳や離乳食が必要です。 |
|||||||||
| 17. | ストレスの主な原因 ■野外飼育や散歩をさせている。 ■引越しや模様変えなどの生活空間(テリトリ)の環境変化。 ■来客、新しい同居者や動物が増えた時。 ■音。猫は聴覚が非常に発達しているので、冷蔵庫のモーターの音でさえ大音量に聞え、ストレスになる事があります。 また大声や怒鳴り声など、喧嘩や言い争いの多い家族の中で暮らす場合も大きなストレスとなります。 ■匂い。主にタバコや香水、柑橘系、メンソール系などキツイ匂いにストレスを感じます。 ■触れる・抱く。日常のケアや病院での診察の為に抱き癖や触らせ癖をつけておく必要はありますが、やたらと構い過ぎるのは大きなストレスとなります。 ■食事やトイレの場所が気に入らない、トイレが汚いなど。トイレや食器など猫の生活空間を一箇所に纏める方がいますが、猫は自分が食事をする場所や汚いトイレでの排泄を酷く嫌います。 【ストレスを感じている時の症状】 |
|||||||||
| ←ホームへ ↑ページのトップへ | ||||||||||